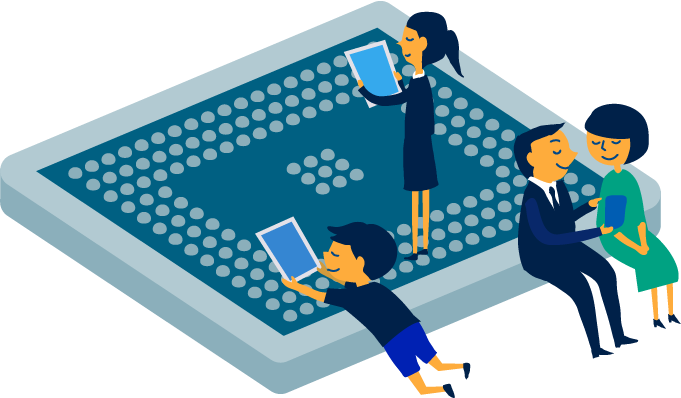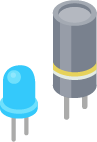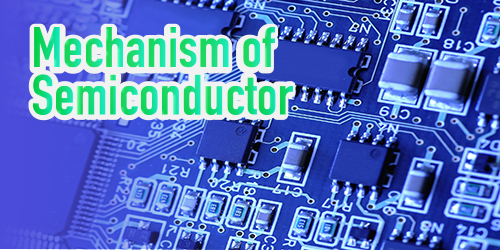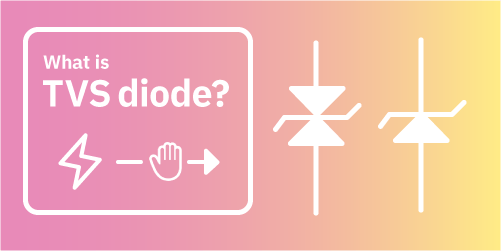「電源」と聞くと、コンセントを思い浮かべるかもしれません。
しかしながらコンセントから流れる電気は交流です。
各種電子回路を動作させるためには、交流を直流へと変換させる電源回路が必要となります。
この電源回路の構成要素のうちの一つがレギュレータです。安定した電圧を保つために欠かせず、近年ますます存在感を示すレギュレータとは一体どのようなものなのでしょうか。
この記事では、レギュレータとは、そしてレギュレータの種類やそれぞれのメリット・デメリット、実際の使用のうえで気をつけたいことなどを解説いたします。

1. レギュレータとは?どんな役割があるの?
「規制」「調整」という意味をもつ英語regulationにちなむレギュレータ。電圧レギュレータや調整器とも称されます。
一定の電源を安定して供給できる電子部品の一つで、主な役割は電圧電流の安定化。
コンセントなどから流れた交流を電源回路に繋ぐと、まず変圧回路で電圧調整し、整流回路で直流に変換。
そして平滑回路で脈流(リプル成分)を低減させ、ほぼ完全な直流にしますが、ここでさらに電圧を安定させるため安定化回路を搭載します。
この安定化回路に当たり、DC/DCコンバータ(直流電流Direct Currentから直流電流にするコンバータのこと)の一種となるのがレギュレータです。
変圧・整流・平滑回路があれば電子回路を動かすことができます。
しかしながら近年、医療分野や自動車、家電など様々な分野において、より安定して信頼性の高い電子システムが求められるようになってきました。
そのため、安定化に一役買うレギュレータは、今ではなくてはならない存在となっております。
なお、レギュレータは、二つのスタイルを持ちます。
リニアレギュレータ、スイッチングレギュレータ
それぞれは、いったいどのような特性を持つのでしょうか。以下でご紹介いたします。
2. リニアレギュレータとは?
抵抗やトランジスタなどの半導体素子の電圧降下を利用し、電圧・電流の安定化を行うレギュレータです。
上記の負荷でアナログ制御するため、アナログ式とも呼ばれます。
特性やメリット・デメリット、使用上で気をつけたいことを解説いたします。
① リニアレギュレータの原理と特徴
リニアレギュレータが電圧を安定させる原理は以下の通りです。
出力したい(電子回路で使用したい)電圧よりも高電圧を入力し、負荷が電圧降下を起こすことによってその希望の電圧を実現しています。
つまり高電圧⇒安定した低電圧に変換させるということです。
回路形式は入力と出力が線型で、レギュレータの中では比較的単純な構造です。
負荷素子を直列接続したものをシリーズレギュレータ、並列接続したものをシャントレギュレータと呼ぶこともあります。
リニアレギュレータは安定して作動するためにはドロップアウト電圧(VDIF)が求められます。
これは、安定動作からドロップアウト(逸脱)しないために必要な入力電圧と出力電圧の差の最小値を指します。
例えばVDIFが1.5Vだとすると、出力したい電圧が5Vであれば少なくとも6.5Vの電源電圧を流さなくては作動しません。
② リニアレギュレータのメリット・デメリット
第一のメリットは回路が単純なため大量生産向きで、低価格帯の個体が多いこと。
また、安定性に優れ、ノイズが少ないことも挙げられます。
デメリットとしては、抵抗素子でも電力を消費するため効率は悪く、大電力回路には向きません。
大きく重くなりがち、といった性質も有します。
また、シリーズレギュレータは電圧降下の際、余剰電圧をジュール熱として放出するため、ヒートシンクなどを使ってきちんと放熱することが求められます。
さらに、ドロップアウト電圧(VDIF)の値が大きくなると、当然ながら負荷素子にかかるエネルギー量はそれだけ多くなり、さらに効率が低下してしまいます。
そこで近年リニアレギュレータにラインナップされているのがLDOです。
Low Drop Outの略で、「低損失型レギュレータ」「低飽和型レギュレータ」とも呼ばれます。
VDIF値を1V以下まで低減することを実現し、高効率を獲得しました。さらに、大きくなりがちなリニアレギュレータの中でも、小型化に成功しています。
一方で使用時の入出力電圧に大きな差があった場合、変換効率が低くなってしまう、といった難点も。
また、ひとくちにLDOと言っても、メーカーによって測定条件が異なり、個体によってVDIF差がばらつき、全てのLDOが必ずしも低ドロップアウトとは言えない、といった議論もあります。
しかしながら携帯用小型電子機器を始めとする低電圧化(小型機器は耐圧が低いため)、そして省電力化への需要の高まりとともに、ますますLDOの必要性が叫ばれています。
加えて、さらなる省電力、及び余剰電圧が少なくなることによる発熱低減を実現したCMOS、レギュレータというものも存在します。
CMOS(シーモス)とはレギュレータで使用する半導体素子をMOS-FET(電界効果トランジスタの一種)で構成したもの。
MOS-FETは集積回路でもおなじみですね。
小型化が可能なため、LDOと並んで現在高い需要を誇っています。
リニアレギュレータは安定化回路の基本であると同時に昔ながらの手法となりますが、このようにメーカーでは研究開発がさかんです。
そのためここで挙げたデメリットも、購入する個体によっては大幅に解決することができますね。
③ リニアレギュレータの種類や使用上の注意
レギュレータは回路形式の複雑さや構成部品の多さから、自作が難しいと言われています。
しかしながら実際の回路で、安定した電圧を送る必要性は決して少なくないでしょう。
そこで、レギュレータ回路を組み込んだ電源用IC(集積回路)を用いることが一般的です。
リニアレギュレータ搭載電源用ICで、最も代表的なものは三端子レギュレータです。
レギュレータと言って、こちらを思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。
その歴史は古く、1960年代の終わり頃に開発されたと言われています。
現在は後述するスイッチングレギュレータが重宝される向きがありますが、わかりやすく使い勝手の良さは魅力。加えてノイズが少ないことによる安定性や信頼性で定評があります。
低価格なのも嬉しいポイントですね。
名称は、三つの端子を持つことに由来します。
IN、OUT、GND(グランド)に対応し、回路内での使用は他のレギュレータより簡単です。
原理としては、目標とするよりも高い入力電圧に対し、余剰電圧をジュール熱に変換。入力より低い出力電圧を安定供給することが可能となります。
代表的な三端子レギュレータ製品に、7800系と7900系があります。
前者が正電源用、後者が負電源用として使うことができ、00の部分には出力電圧値が入ります。
例えば7805であれば、5Vの出力電圧を提供できる、ということになります。
かつては5V以上の品種が一般的でしたが、低電圧対応の回路が増えたことから3.3Vのものも製造されています。
なお、出力電圧を可変できるタイプも存在します。
変換効率は高くありません。
また、発熱するので、入出力電圧差が大きい場合はそのまま使えないこともしばしばです。
放熱のためのヒートシンクの取り付けにはスペースをとるので、回路の小型化にも不向きとなります。
一方でLDOやCMOS化された個体が販売中で、これらの個体は小型携帯電子機器に対応できるほどのサイズ感を誇ります。
先ほども触れましたが、リニアレギュレータは「昔ながら」でありながらも進化を遂げ続けています。
■三端子レギュレータを使用するうえで気をつけたいこと
三端子レギュレータは基本的には容易に使えますが、以下の二点はご留意ください。
-
◆入力電圧と出力電圧に差があると発熱が大きくなる
⇒ヒートシンクなど放熱や過電流保護回路を内蔵しているものを選ぶか、取り付けましょう。 また、規格表に記載された最大入力電圧を確認し、超えないように気をつけてください。これを超えて印加してしまうと、破損や事故が発生しかねません。
-
◆入出力電圧差が必要
⇒前述のようにドロップアウト電圧と呼ばれる、入出力電圧差を超えないと機能しません。一般的には約1.5V以上が必要とされていますが、個体によってばらつきがあるので規格表で確認しましょう。 ただし、差が大きすぎると発熱量も多くなります。 近年では電圧差を抑えエコを実現した個体(LDO)も出ていますので、消費電力が気になる方は電圧差に気をつけてみてください。
-
◆異常発振の可能性
⇒トランジスタやFETなどの素子は増幅作用を持ちます。 増幅作用とは電源電圧から供給された電気エネルギーをより大きな出力の電気信号に変換する働きで、波形のひずみや温度変化などにより増幅度が変化してしまうことがあります。これを防ぐために出力の一部を入力側から見て逆位相に搭載・増幅を正す「負帰還(ネガティブフィードバック)」を掛けることがあります。 出力電圧を安定させるため、リニアレギュレータにおいては負帰還を利用しますが、この負帰還は発振作用(過増加などを引き起こすもの)が出てしまうケースが見られます。 対処法は規格表やデータシートに記載されているので、確認しましょう。
3. スイッチングレギュレータとは?
リニアレギュレータが負荷素子を用いて電圧制御をしていることに対し、スイッチの高速オンオフによって制御・安定化を行うレギュレータがスイッチング方式です。
電圧効率や信頼性の高さから、現代社会における安定電圧の立役者的存在となっています。
① スイッチングレギュレータの原理と特徴
スイッチングレギュレータの原理は以下の通りです。
インダクタ(コイルのこと)とスイッチング素子を用いたスタイルで、オン時にコイルに蓄えたエネルギーをオフ時に負荷に向けて放出する、など、出力電圧に合わせてオンオフ比率を制御することによって電圧安定を得ます。
例えば出力電圧が想定よりも高くなった場合、スイッチング素子をオフにしてエネルギーを負荷に向けて放出。電子回路にかかる電圧を制御する、といった具合です。
コイルとともに、コンデンサが使われることが一般的です。
コンデンサとは充放電が可能な電子部品の一つ。よって、リニアレギュレータとの大きな違いとして、入力電圧より出力電圧を高くすることも低くすることも可能となりました。なお、反転型と言う、昇降圧両方に対応した個体もラインナップされています。
スイッチングレギュレータもまたいくつかの分類があります。
最も大きな分け方として、「非絶縁型」のチョッパ形、「絶縁型」のコンバータ形が挙げられます。
チョッパ形はchopper「切り刻む」が語源です。
スイッチングレギュレータの基本回路形式で、電圧の入力側と出力側が絶縁していない回路形式を採ります。
コンバータ形は入力側と出力側を絶縁した形式のスイッチングレギュレータです。
漏電事故などで感電することを防ぐために取り入れられた手法で、前述のチョッパ形にトランス(変圧器)を挟むことで実現しています。
現在、多くの家電製品や医療機器などは、このコンバータ形が採用されます。
この二種類からさらにフライバック型、フォワード型などに分類することもできますが、これは回路形式や構成部品による違いです。
非常に複雑なため、個人で一から回路を組むのはかなり大変。
リニアレギュレータ同様、様々なメーカーがスイッチングレギュレータを搭載した電源用ICを製造しているので、既製品を購入しましょう。
② スイッチングレギュレータのメリット・デメリット
スイッチングレギュレータのメリットはリニア方式に比べ、何よりも効率の高さが挙げられるでしょう。
これは、電力の主な損失(消費)はスイッチとダイオードのため、消費電力が少ないことも示唆します。
昇降圧を選択できるのもいいですね。降圧させることが多いかもしれませんが、電池など低電圧から入力するケースの時は便利です。
また、高速スイッチングにより入力電圧をパルスに変換するため、発熱を抑えることも可能です。
加えて小型化が容易で、個体によってはリニアレギュレータの1/10から1/2に抑えられます。
一方で、もちろんデメリットもあります。
まず、回路構成が複雑で、リニアレギュレータに比べ生産にコストがかかり価格が高くなります。
スイッチング素子やダイオード、トランジスタといった構成要素が多くなることも関係しているでしょう。
これと併せて使い方の難易度も上がります。
また、スイッチングを繰り返すためノイズは大きくなり、安定性もリニアレギュレータの方が高くなります。
③ スイッチングレギュレータの規格や使用上の注意
現在製品化されているスイッチングレギュレータは様々な種類が存在しますが、実装タイプや、既にスイッチングレギュレータが組み込まれた電源回路から選択することとなります。
そのため用途や構築したい電子回路のサイズに合わせてお選びいただくことが可能です。
しかしながらデータシートを見るとかなり煩雑。
初めてスイッチングレギュレータに触れる方は、何がなんだかわからないかもしれませんね。
そこで、購入・使用の際に抑えておきたい規格を解説いたします。
-
■入力電圧範囲
- 文字通り、動作させることができる入力電圧の範囲です。 電源電圧や使用する回路によって必要な出力電圧は異なるため、仕様に合うものを見つける必要があります。 最大値と最小値が記載されており、最小値を下回る電圧だと作動しないだけでなく、異常動作を見せる場合もあるので、確認してください。 なお、最大定格とは異なります。
-
■出力電圧範囲
- 出力できる電圧の範囲を指します。固定タイプのレギュレータには存在しません。
-
■出力電流
- 低電圧大電流が必要とされる電子回路にとって、出力できる電流量の確認は大切です。 最小値のみの保証がなされる場合と、最大値も保証しているものとがあります。 希望する出力電圧に余裕をもった値が必要とされます。超えてしまうと発熱し、破損や劣化の原因となります。 出力電流表記とスイッチング電流表記とがあり、後者は連続的に供給できる電流を指しません。
-
■スイッチング周波数
- スイッチング周波数とはオンオフによって制御する信号の周波数のことで、数十kHz~数MHz程度の値となります。 この周波数が高いとオンオフが頻繁になり、より小型化が可能です。またリプル成分を低減する、電圧変動へのレスポンスが速くなる、といったメリットがあります。 一方で高ければ優秀、というわけではありません。スイッチング周波数が高いものは変換効率が低下します。また、EMI(放射電磁雑音)が増加し、他の回路に影響を与える可能性もあります。 なお、この影響はフィルタによって低減することもできます。
- データシートにTaまたはTjという表記が見られるかと思います。 これはレギュレータが動作することのできる温度範囲で、Taは周囲温度Ambient Temperature、Tjはジャンクション温度Junction Temperatureを意味します。 周囲温度は文字通り周囲の環境での温度で、レギュレータの発熱は加味されていません。ジャンクション温度は動作できる最大温度を示しており、これを超えると機能が著しく落ちたり高温発熱・発火したりする可能性があります。 周囲温度はもちろんのこと、負荷電流によって発生する熱抵抗を考慮してください。
■動作温度範囲
▶ヒューズの購入はこちらから
▶電源レギュレータ DC/DCスイッチングコントローラの購入はこちらから
▶電源レギュレータ DC/DCスイッチングレギュレータの購入はこちらから
▶電源レギュレータ リニア(LDO)の購入はこちらから
▶電源レギュレータ リニア・スイッチングの購入はこちらから
▶電圧レギュレータ リニアトランジスタドライバの購入はこちらから
▶電圧レギュレータ 特殊用途の購入はこちらから
▶パワーマネージメントの取り扱いカテゴリ一覧はこちらから
▶集積回路・ICに関するCoreStaffONLINE取扱い一覧はこちらから
5. レギュレータについてよくある質問
Q.レギュレーターとは何ですか?
A.レギュレーターは、電子回路の一種で、出力電圧や電流を一定に保つ装置です。主にリニアレギュレーターとスイッチングレギュレーターの2種類があります。入力電圧や負荷の変動に関わらず、安定した電圧を供給し、電子機器の正常な動作を確保します。電源回路や電圧制御に広く使用され、様々な電子機器に不可欠な部品です。
Q.レギュレータの役割は?
A.主な役割は、入力される電圧や圧力を安定した一定の値に調整することです。電子回路では、入力電圧を目的の出力電圧に変換し、安定化します。
Q.電圧レギュレータは何に使いますか?
A.安定した電源供給、電子機器の過電圧保護、電池駆動機器の電圧補償、異なる電圧レベル間の変換、電源ラインのノイズ除去などに使用されます。これにより、電子機器の正常動作を確保し、性能を向上させます。
Q.レギュレータとトランスの違いは何ですか?
A.トランスは主に交流電圧を変換するために使用され、巻き数比に応じて電圧を上げ下げします。一方、レギュレータは電圧を安定化させる役割を持ち、入力電圧の変動や負荷の変化に関わらず、一定の出力電圧を維持します。レギュレータは直流電圧の制御に使用され、電子機器の安定動作に不可欠です。
Q.レギュレータが壊れるとどうなりますか?
A.電圧や圧力の制御ができなくなり、機器の誤作動や故障を引き起こします。例えば、自動車の電圧レギュレータが故障するとバッテリーが過充電や電力不足に陥り、エンジン不調の原因になります。ダイビング用のレギュレーターなら、空気供給が不安定になり、呼吸困難を招く危険があります。
重要概念まとめCheck it!
レギュレータとはどのようなものか。回路内での役割やリニア式とスイッチング式に分類されること。それぞれの特性やメリット・デメリットなどをご紹介いたしました。
復習を兼ねて、本稿に出てきた重要用語のクイズに挑戦してみましょう!
答えは一番下に掲載しております。
問題
- レギュレータの回路内での役割とは?
- リニアレギュレータの動作を安定させるために必要な入力電圧と出力電圧の差は何と言う?
- リニアレギュレータが搭載された電源用ICで最も代表的なものとは?
- スイッチングレギュレータのメリットを二つ以上挙げてください。
- 入力電圧範囲の最大値を超えるのが怖いから最小値を下回る電圧を印加した。この行為は〇か×か?
答えはこちら!
- より安定した直流電流を電子回路に送る
- ドロップアウト電圧(VDIF)
- 三端子レギュレータ
- 高効率,出力電圧より入力電圧を上げることができる,発熱を抑えられるためヒートシンクを必要とするシーンが少ない、など。
- ×
個人でも法人でも
半導体がひとつから買える
半導体の通販サイト
CoreStaff ONLINE
【コアスタッフオンライン】