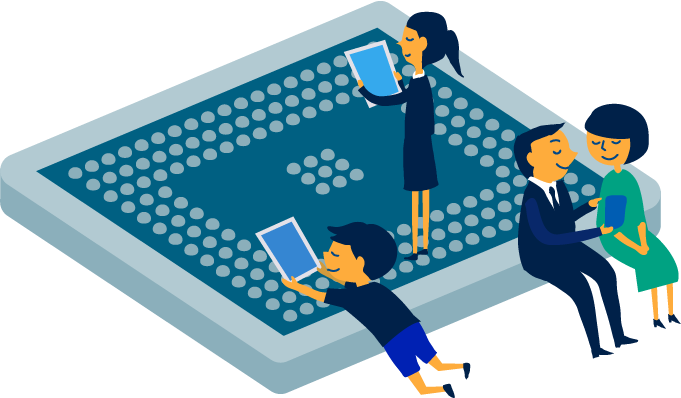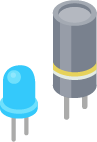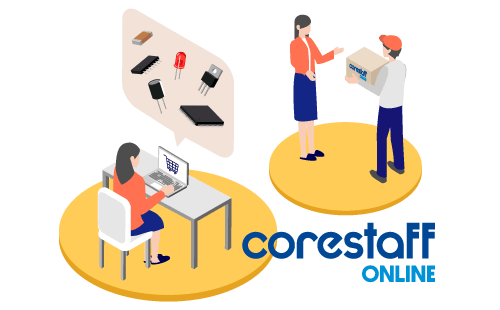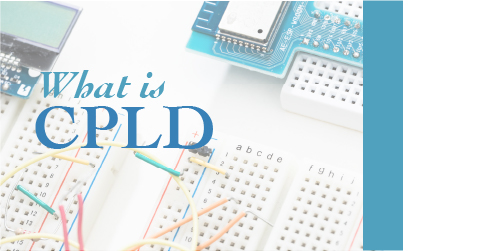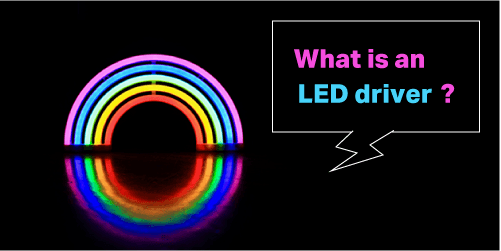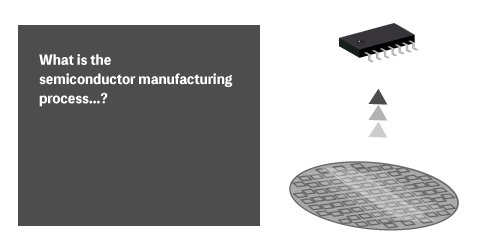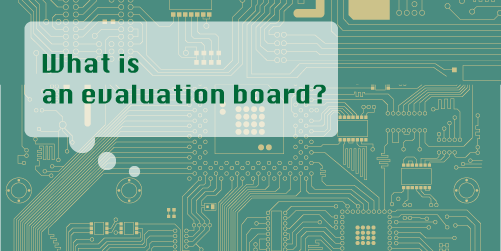日常生活では当たり前に使っているコネクタ。
はんだ付けなどと異なり何度でも脱着が容易で、汎用性が高いものであれば一つ持っているだけで様々な機器同士をつなぐことができる、優れモノです。
そんなコネクタは何気なく使われていますが、その種類はきわめて膨大です。
例えばスマートフォン用(その中でもApple用途、Andoroid用途など様々)、無線LAN用、ゲーム機器用、音響用など、それぞれに適したコネクタがあり、国内外の規格で標準化されているものもあれば、メーカー独自のものも存在します。
いったい私たちの身の周りには、どれほどのコネクタが溢れているのでしょうか。
そこでこの記事では、USBコネクタやHDMIコネクタ、光コネクタなど、身近なコネクタの種類とその形状についてそれぞれ解説いたします。
※掲載しているコネクタ形状は代表的なものであり、全ての電子機器に適応するとは限りません。
インターフェースのご購入時には、お使いの機器のコネクタ形状や対応規格を必ずご確認くださいませ。
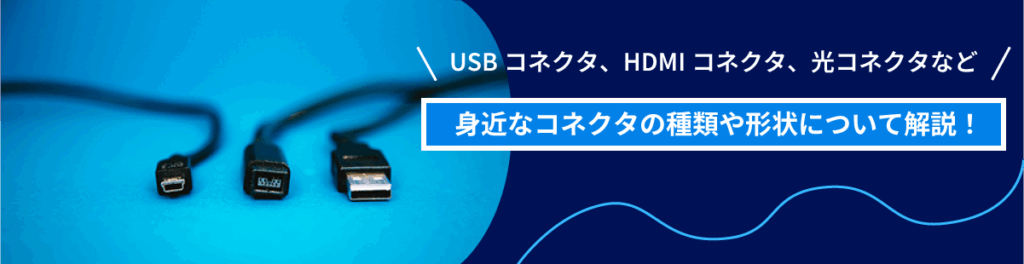
目次
1. プラグ?レセプタクル?コネクタの各名称について
「コネクタ貸して!」なんて会話を繰り広げる時、電線にあたるケーブルも一緒に指すことがありますが、コネクタは正確には電線あるいは機器を「挿す箇所」「挿される個所」を意味します。 さらにそれぞれの各所には名称があります。
まず、「挿す箇所」をオスコネクタと呼ぶことがあります。そして対義語として「挿される箇所」のメスコネクタがあります。
オスコネクタの代表格がプラグでしょう。突起が付いたタイプが一般的ですが、受け口がついたメスタイプのプラグもあります。
また、メスコネクタと言えばジャックが最も有名な用語です。プラグを挿すための受け口に当たります。
また、レセプタクルという用語もよく出てきます。やはりメスタイプの差込口を指し、ジャックと同義語として用いられることもありますが、厳密には機器の外装などに直接実装されているものをレセプタクルと呼びます。
レセプタクルの対義語がヘッダーとなり、ピンが出ているコネクタとなります。
メスコネクタには他にソケットも挙げられます。
これまたジャックと同様のコネクタですが、通常、電子基板上に各種チップを実装するための受け口を指します。
なお、冒頭でもご紹介したように、コネクタには規格があるため形状の合わない製品同士を接続することはできません。
しかしながらアダプタと呼ばれる変換コネクタを用いれば、アダプタが仲介のような役割を果たし、異なる製品同士を組み合わせることも可能です。
2. 各種コネクタを解説
それではコネクタ7種類を、それぞれコネクタ形状とともに解説いたします。
なお、種類と言っても、各名称はコネクタの商品名ではなく、規格やある分野で用いられるコネクタとしての総称を指すことなど様々です。
① USBコネクタ
最も広く普及しているコネクタの一つがUSBです。
Universal Serial Busの略称であり、1996年のUSB1.0から始まり、2020年現在はUSB4の世代まで発展してきました。
ちなみに「シリアルバス<Serial Bus>」というのは信号の伝送方法です。
IT用語ではバスは「経路」や「信号線」を意味しており、バスが複数あるパラレルバスと一本線となるシリアルバスに分かれます。
パラレルバスが複数経路を使って複数信号を平行して伝送するのに対し、シリアルバスは一本線で一つずつのデータを伝送します。
前者は伝送のタイミングを合わせるために、全ての信号がスタート地点に到達するのを待たなくてはならず、その分タイムロスがあります。
一方のシリアルバスはその必要がないため、高速で高効率な信号伝送として、現在では主流となっています。
そんな信号伝送を行うUSBですが、何よりの魅力は多くの電子機器でUSB規格を採用している、という汎用性にあります。
USBコネクタ、色々なところで見かけますよね。
ほとんどのメーカーのパソコンにはUSBポートが搭載されており、マウスやキーボードといったペリフェラルから他の電子機器への充電、通信、データ転送を担っています。
USBコネクタの形状は大きく分けて「USB」「Mini USB」「Micro USB」があります。
さらにその中でType-A・Bに細分化されています(USBはType-Cまで)。
以下にそれぞれの用途を示します。
- USB Type-A:
- パソコン用途。ケーブルの端のどちらか一方はこのタイプであることが多い。
- USB Type-B:
- パソコン周辺機器
- USB Type-C:
- Mac Book、Androidなど。パソコンにも周辺機器にも使えるため、ケーブルの両端が同形状。どちらを挿しても対応できる。さらに言うと後述するHDMIなど、これまで全く異なる規格であったコネクタとも互換性を持つようになった。
- Mini USB Type-A:
- かつてはデジタルビデオカメラなどに用いられていましたが、現在はあまり流通していません
- Mini USB Type-B:
- モバイル機種。デジタルカメラやモバイルバッテリーなど
- micro USB Type-A:
- 現在はあまり流通していません
- micro USB Type-B:
- Androidやタブレットなど
その他micro USB Super SpeedやLIGHTNINGなどが存在します。
② HDMIコネクタ
HDMIとはHigh-Definition Multimedia Interfaceの略称で、高精細度マルチメディアインターフェースという意味です。
2003年、ソニー、東芝、トムソン、パナソニック、日立製作所、シリコンイメージ、フィリップスで共同開発して標準化された規格で、誕生以前はDVI(Digital Visual Interface)コネクタが用いられてきましたが、それを発展させたものとなります。
まもなく20年にもなりそうな歴史の中で世代交代がありましたが、同一のコネクタ・ケーブルを使用してきました。
こちらは映像・音声のデジタル信号伝送用インターフェースとして、非常によく普及している規格となります。
用途はパソコン、スマートフォン、デジタル家電、ゲーム機器等のデータをデジタル信号で液晶ディスプレイへ転送することにあります。
例えば上述した機器に保存された映像をもっと大きな画面で見たい時などに便利。また、映像のみならず音声も同一のHDMIコネクタで一緒に伝送できる、というのもミソです。
かつては別々のケーブルが必要でしたが、それがまとめられ、かつ配線の少ない小型軽量化に成功した優れモノと言えるでしょう。
ファイルフォーマットが「非圧縮式」であるため、オリジナルの音質や映像がそのまま伝送されることとなり、ほとんど劣化しません。
そのため通信手段として用いられることもあります。
なお、コネクタの形状はA~Eの5タイプに分かれます。
- タイプA:
- パソコンやディスプレイなど据え置き機器用。最も一般的なHDMIのコネクタ。19ピン
- タイプB:
- 現在は流通していません
- タイプC:
- HDMI-miniとも呼ばれており、タイプAをダウンサイジングしたコネクタ。デジタルビデオカメラなどに用いられる。19ピン
- タイプD:
- スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器用。タイプCよりもさらに小さい。19ピン
- タイプE:
- 自動車専用。19ピン
③ DVIコネクタ
前述の通りDVIコネクタとは、HDMI以前に用いられていた映像を伝送するためのコネクタ規格です。
HDMIと同様に非圧縮式のファイルフォーマットを採るため伝送途中でノイズの影響を受けず、データが劣化しないことが何よりの魅力。
2003年にHDMIがリリースされるまではデジタル映像に特化した唯一のインターフェースとして世界中で使用されました。
現在ではあまり使われませんが、HDMIと伝送方式などで共通するところも少なくなく、全てのデジタル映像ではありませんが変換コネクタを通じて互換性を持たせることが可能です。
コネクタとしては三種挙げられ、デジタル映像信号に対応するDVI-D、アナログ映像信号に対応するDVI-A、その両方に対応可能なDVI-Iとなります。
④ 光コネクタ
光コネクタは光ファイバー同士を接続するために用いられるコネクタの総称です。
光ファイバー自体は石英ガラスやプラスティックで作られたきわめて細い繊維で、それを用いることで電気信号に比べて高速&長距離という利点を持ちます。
あらゆる産業で注目されており、近年では光ファイバーを用いてレーザー光源の照明が開発されたり、さらには地震観測にも成功したりしているとか。
そんな光インターフェースに欠かせない光コネクタ。これがなければ光軸がずれてしまい、十分な機能を果たせません。
光ファイバーはコアと呼ばれる光軸を接続することで高速通信を可能にしており、 光コネクタは、光ファイバーの先端を光コネクタ専用のフェルールと呼ばれる接合端子で固定した構造をしています。
さらに、光アダプタを用いることで光ファイバーと機器同士を接続させます。
ちなみに光ファイバーは産業用途がメインであった時代が長く(かつては高価格で、精密な設計・組み立てが求められたため)、防塵キャップや専用クリーナーなども他コネクタと比べて広く普及しています。
光コネクタもまたその種類は様々です。
最も一般的な光コネクタはSCコネクタです。プッシュプル方式で操作性も良く、LANを始めとした通信機器によく用いられますね。
ちなみに光の伝搬モードによって「シングルモード」「マルチモード」に分類されており、機器によってどちらが適しているか異なります。
データシートを確認しましょう。
また、FCコネクタもよく用いられます。FCコネクタは光通信の黎明期から用いられてきたコネクタで、ねじ締め方式であることが特徴です。
そのため光軸がずれずにしっかりと接続することが可能です。
その他にも小型のLCコネクタや複数の光ファイバーを接続するのに適したMPOコネクタなどが存在します。
なお、異なるタイプのコネクタでも互換性を持つケースもあるので、繰り返しになりますがデータシートをしっかり確認してください。
⑤ 圧接コネクタ
圧接は加工方式を指しますが、そこにコネクタがついた場合、ケーブルに接続される電気コネクタを意味します。
構造としてはケーブルの絶縁体部分に接続され、文字通り物理的に圧接して食い込ませるように固定されています。
ケーブル同士をしっかりと接続することができ、かつ作業時間も短く特別なスキルがいらないと言われています。
かつては産業用途の通信やコンピュータシステムのパーツ同士の接続に用いられていました。
とりわけ低電圧機器での用途が多かったです。しかしながら現在では家庭などでも利用されており、電話機などで見ることができます。
ちなみに似た用語で圧着というものがありますが、こちらはケーブルへの接続方法が圧接とは異なります。
⑥ モジュラーコネクタ
電話回線やインターネット回線のモデムなどでしばしば「モジュラージャック」という用語を耳にしたことはありませんか?
モジュラージャックはアメリカ連邦通信委員会に登録される規格のうちの一つで、通信ケーブルに関するインターフェースを指します。
正式な規格名称は「RJ-11」となります。電話などの他、オーディオ機器やコンピュータの周辺機器の接続口としても幅広く用いられてきました。
そのコネクタに当たる部分がモジュラーコネクタです。
ただし英語圏では「モジュラーコネクタ」という言い方もまた一般的です。
1960年代、ウェスタン・エレクトリック・カンパニーによって開発されたインターフェースで、透明のプラスティックでできた角型プラグを持つこと、そして6ピンコネクタであることが特徴です。このコネクタは2線式のケーブル末端に取り付けられており、機器の差込口にツメを押し込むようにして挿入します。
非常に操作性が良く、また脱着が容易であるにもかかわらずツメによってしっかりと固定できることから、きわめて信頼性の高いコネクタと言えます。
⑦ 表面実装のためのコネクタ
最後に、明確な規格名ではありませんが、プリント基板に表面実装する際に用いられるコネクタをご紹介いたします。
ちなみに前述の通り、基板上の差込口は「ジャック」とは呼ばずに「ソケット」ということが一般的です。
■基板間コネクタ
基板対基板コネクタとも呼ばれます。
文字通りプリント基板同士の接続に用いられるコネクタで、当初の設計よりも回路を追加したくなった時などに便利です。
機器のスペースや製品によって積層したり、直角に接続したりする場合があります。
■バックプレーンコネクタ
バックプレーンとは複数のコネクタを一つの基板上にまとめた電子回路のことです。
各種コネクタはそれぞれに対応したピンがリンクされており、相互接続することができます。こういった複数のバス(経路)を持つことから、バックプレーンシステムと呼ばれることもあります。
ちなみにマザーボードと同様の機能を果たすこともありますが、バックプレーンにCPUのケイ酸処理・制御・ストレージが備わっているわけではないため、明確に区別されています。
マイコンの黎明期、プロセッサや拡張カードにバックプレーンコネクタはよく用いられていました。
ケーブルと比較して信頼性が高く、かつ頻繁な脱着が可能であったためです。
また、通信以外でもプラグインした拡張カード群へ電源供給を行うことが可能です。
■FPCコネクタ
FPCとはフレキシブル・プリント基板のことです。
その名の通り柔らかく柔軟性に富んだ基板で、リジッド(rigid)などと称されることもあります。
もちろん耐久性も考慮されているので、小型機器や精密・精緻な設計が必要な電子回路での配線でよく用いられてきました。
配線のみならず、基板間を接続することも可能です。
コネクタはFPC専用のものとなりますが、メーカーによって多彩なラインナップが展開されています。
何を接続するか、コネクタの数、定格など、所望の電子工作に適した一つを選びましょう。
■FFCコネクタ
FFCとはフレキシブル・フラット・ケーブルを指します。
一定間隔で並べられた複数の平らな導体を、きわめて薄いフィルム上の絶縁体(プラスティックフィルムなど)で挟み込み、補強された構造をしています。
こちらもフレキシブルの名の通り柔軟性に富んでいるたえ、高度な精密機器などでよく用いられます。
FFCコネクタもまたいくつかのラインナップがあるので、用途に合ったものを選ぶようにしましょう。
▶USB、DVI、HDMIコネクタの購入はこちらから
▶光コネクタの購入はこちらから
▶モジュラーコネクタの購入はこちらから
▶バックプレーンコネクタの購入はこちらから
▶FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタの購入はこちらから
▶コネクタ・インターフェースに関するCoreStaffONLINE取扱い一覧はこちらから
CoreStaff ONLINEのコネクタに関連するメーカー一例は
3. コネクタについてよくある質問
Q.「コネクタ」とはどういう意味ですか?
A.コネクタとは、電気・電子機器やネットワーク機器を接続するための部品や端子のことです。英語の 「connector」 は、「接続するもの」や「つなぐ役割を持つもの」という意味を持ちます。電源や信号を正しく伝達する役割があり、USB、HDMI、LAN、オーディオ端子など、さまざまな種類があります。
Q.コネクタとはケーブルのことですか?
A.コネクタはケーブルそのものではなく、ケーブルの端に取り付けられた、機器同士を接続するための部品です。LANケーブルの先端にあるLANポートに接続するための端子を指します。
Q.「コネクタ」の言い換えは?
A.「コネクタ」の主な言い換えとしては、「つなぎ」「繋ぎ」「プラグ」「接栓」などがあります。また、「接続」「連結」「結合」といった類語も使用されます。
Q.コネクタに液体が付着、どうしたらいいですか?
A.コネクタに液体が付着した場合、まず電源を切り、接続を解除してください。乾いた布やティッシュで優しく拭き取り、自然乾燥させます。水分が残るとショートや腐食の原因になります。
Q.コネクタをドライヤーで乾かすとどうなる?
A.コネクタをドライヤーで乾かすと、冷風なら速く乾燥できますが、温風は高温で部品を傷める可能性があります。特にプラスチック部分が変形したり、内部のはんだや絶縁材が劣化したりする恐れがあります。安全に乾燥させるには、自然乾燥や乾燥剤の使用が望ましいです。
4. 重要用語まとめCheck It!
各種コネクタについて解説いたしました。
広く普及しているUSBコネクタやHDMIコネクタ。光通信に欠かせない光コネクタ。表面実装で用いられるバックプレーンコネクタやFPCコネクタについて、ご理解いただけたでしょうか。
最後にコネクタの復習を兼ねて、以下のクイズにチャレンジしてみませんか?答えは一番下に掲載しております。
問題
- レセプタクルとは?
- USBコネクタのうち、パソコン周辺機器に用いられる種類はどれ?
- HDMIコネクタの中で最も普及しているものはタイプAである。〇か×か?
- 光コネクタに用いられる専用の接合端子を何と呼ぶ?
- プリント基板上の差込口を何と呼ぶ?
答えはこちら!
- 機器の外装などに直接実装されるメスタイプの差込口
- USB Type-BやUSB Type-Cなど
- 〇
- フェルール
- ソケット
個人でも法人でも
半導体がひとつから買える
半導体の通販サイト
CoreStaff ONLINE
【コアスタッフオンライン】