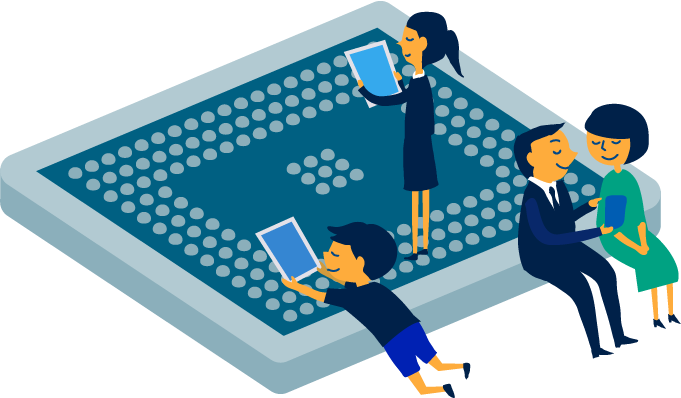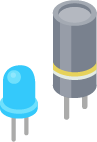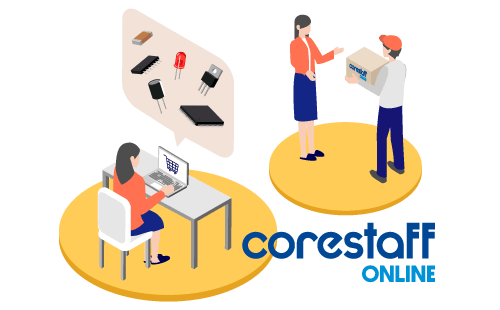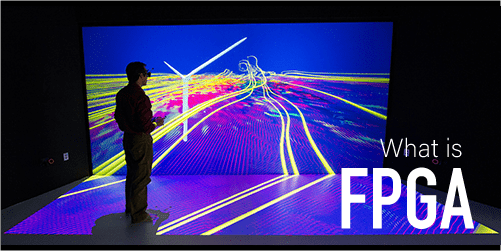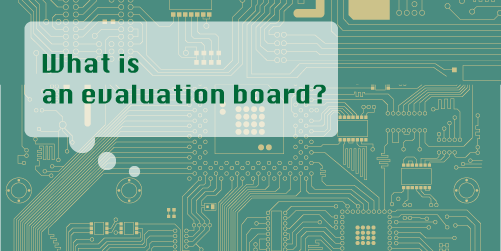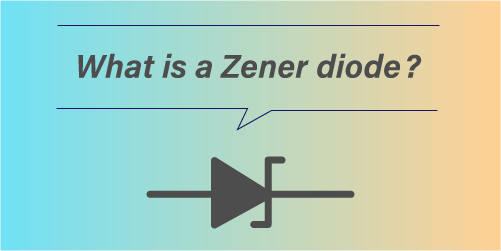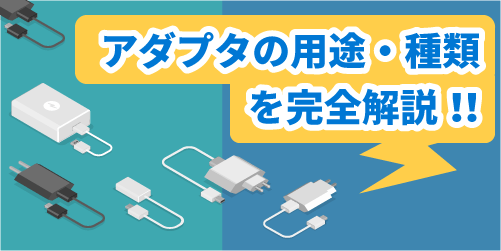トランジスタとは何でしょうか。
どのような役割をしていて、どのような用途があるのか、仕組みや原理から詳しく解説していきます!
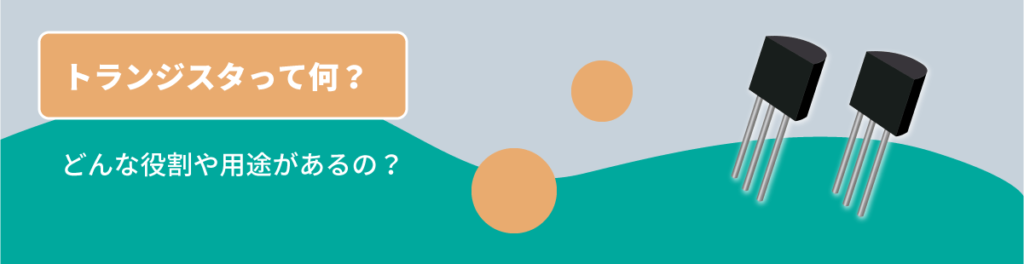
目次
1. トランジスタとは?
トランジスタは電気の流れをコントロールする部品で、いろんな電子回路に利用されるとても重要な部品です。
「トランジスタ(Transistor)」は、小さな電気信号を大きくする増幅作用と、電気信号のONとOFFを切り替えるスイッチ作用を持っています。
そもそも「トランジスタ」は、軍事レーダーを検知する研究から発明されました。
発明された1948年の当時は「真空管」を用いて軍事レーダーの微弱な電波を増幅していましたが、ゲルマニウムに微量の不純物を加えたものを組み合わせると電流の増幅作用が生まれることを発見したことから始まりました。
「トランジスタ」は「真空管」よりも消費電力が少なく、寿命も長いというメリットを備えていますので、軍事用途だけでなく民間用途にも利用範囲が一気に広がっていきました。
この「トランジスタ」が開発されるまでの電子機器には「真空管」が使われていました。
小型化が難しかった「真空管」に代わって「トランジスタ」が開発されたことによって、電子機器を小型化、高性能化させることができるようになりました。
真空管ラジオやブラウン管テレビなどに代わり、携帯用ラジオや薄型液晶テレビが開発できるようになったのもこのためです。
そして、昔は一部屋を占領するほど大きかったコンピュータを手のひらサイズにまで小型化できたのも「トランジスタ」のおかげです。
2. トランジスタの用途について
トランジスタはどのように利用されるのか、用途について解説していきます。
① マイクロプロセッサー
「マイクロプロセッサー」は、「トランジスタ」を超小型のスイッチとして利用しています。
「10進法」で計算している人間とは違って、コンピュータは「2進法」を使用しています。
2進法の「0」はスイッチOFF、「1」はスイッチONとして置き換えられます。
コンピュータはこの「0」と「1」の特定の並び方によって、さまざまな文字や図や色などを表現しています。
「マイクロプロセッサー」は、「0」と「1」によって表現されるさまざまなデジタルデータを、膨大なスイッチの組み合わせによって超高速に計算したり加工したりしています。
② 集積回路
1つの半導体チップ上に「トランジスタ」などの電子素子を多数作り込んだものを「集積回路(IC)」と呼んでいます。
「集積回路」はインテル社の創始者の一人としても知られているロバート・ノイスと、テキサス・インスツルメンツ社のジャック・キルビーによってそれぞれ発明されました。
その後、2人が持つ基本特許に基づいて、「集積回路」は急速に進化を遂げています。
半導体チップに集積される「トランジスタ」の数は着実に増え続け、最新のものでは10億個を超える膨大な数の「トランジスタ」が集積されています。
3. トランジスタの仕組みや原理
「トランジスタ」は、2つPN接合を持つ三層構造になっています。
電荷を集める「コレクタ(Collector)」と、制御の土台となる「ベース(Base)」と、電荷を放出する「エミッタ(Emitter)」の3つの電極を持ち、ベース電流によってコレクタ電流を制御するようになっています。
「トランジスタ」は、PN接合の組み合わせ方法によって、「NPN型トランジスタ」と「PNP型トランジスタ」に分類されます。
これらを合わせて「バイポーラトランジスタ(:2極性トランジスタ)」とも呼ばれます。
また、「バイポーラトランジスタ」の他に、「FET(Field Effect Transistor:電界効果トランジスタ)」があります。
「バイポーラトランジスタ」が2種類の電荷を使うのに対して、1種類の電荷しか使わないので「ユニポーラトランジスタ(:単極性トランジスタ)」と呼ばれます。
「トランジスタ」が電流で動作するのに対して、「FET」は電圧で動作するという違いがあります。
そのため「FET」は、「コレクタ」「ベース」「エミッタ」ではなく、電荷を排出する「ドレーン(Drain)」と、電荷を制御する「ゲート(Gate)」と、電荷の源になる「ソース(Source)」の3つの電極を持ちます。
「FET」は、上記の3つの電極を持つ「接合型FET」と、「ゲート」を2つ持つ「絶縁ゲート形FET(MOS:Metal Oxide Semiconductor)」に分類され、更に電荷に応じて「Nチャンネル」と「Pチャンネル」に分類したり、構造の違いによって「エンハンスメント形」と「デプレッション形」に分類したりします。
一般に、単に「トランジスタ」と言った場合は、「ハイポーラトランジスタ」を指すことが多いです。
4. トランジスタの種類について
半導体の組み合わせや構造によって、さまざまな特性を持つトランジスタが作られています。
分類方法もさまざまですが、一例を以下にあげておきます。
① バイポーラ型トランジスタ
電流の変化で、電圧の変化を取り出します。
一般電子回路に使う「小信号用」、モーター回路などに使う「大電流用」、パワーアンプ回路などに使う「パワー用キャンタイプ」、電源回路などに使う「パワー用モールドタイプ」などがあります。
② ユニポーラ型トランジスタ
電圧の変化で、電流の変化を取り出します。
一般電子回路に使う「小信号用FET」、電源回路などに使う「パワー用FET」などがあります。
③ フォトトランジスタ
光信号によって電流を制御します。光センサ回路などに使われます。
④ サイリスタ
一度、電気が流れるとオンのままになります。電力制御回路などに使われます。
トランジスタについてよくある質問
Q.トランジスタは半導体ですか?
A.トランジスタは半導体素子です。半導体材料(主にシリコン)を使用しており、電流を制御する役割を果たします。
Q.トランジスタとは何をするためのものですか?
A.トランジスタは、電流の増幅やスイッチングを行うための電子部品です。主に、入力された微弱な電流を増幅して出力する増幅器や、オン・オフの切り替えによって信号を制御するスイッチとして使用されます。これにより、オーディオ機器やコンピュータ、通信機器など、さまざまな電子機器で重要な役割を果たします。
Q.トランジスタの仕組みは?
A.トランジスタは、エミッタ、ベース、コレクタの3つの部分で構成され、半導体材料を使って電流を制御します。ベースに小さな電流を加えると、エミッタからコレクタへ大きな電流が流れ、信号を増幅します。また、スイッチとしても動作し、ベースの電流でエミッタとコレクタ間の電流の流れをオン・オフできます。これにより、さまざまな電子機器で使用されます。
Q.FETとは何の略ですか?
A.FETは「Field Effect Transistor(電界効果トランジスタ)」の略です。FETは、電界によって電流の流れを制御するトランジスタの一種で、主に増幅やスイッチングに使用されます。FETは、ゲート、ソース、ドレインの3つの端子を持ち、ゲートにかけた電圧によってソースとドレイン間の電流を調整します。
Q.FETの寿命はどのくらいですか?
A.FET(電界効果トランジスタ)は半導体素子であり、機械的な部品ではないため、通常の意味での「寿命」は存在しません。半導体素子は物理的な摩耗がないため、理論的には無限に動作し続けることができます。ただし、外的な要因(過電圧、温度の極端な変化など)が影響すると、劣化や故障が起こることがありますが、それでも「寿命」という言葉は正確には適用されません。
とても重要な部品のひとつであるトランジスタについて知識を深めていただけましたでしょうか。
CoreStaff ONLINE<コアスタッフオンライン>でもトランジスタを豊富に取り扱っております!
お気軽のお問い合わせください!
個人でも法人でも
半導体がひとつから買える
半導体の通販サイト
CoreStaff ONLINE
【コアスタッフオンライン】